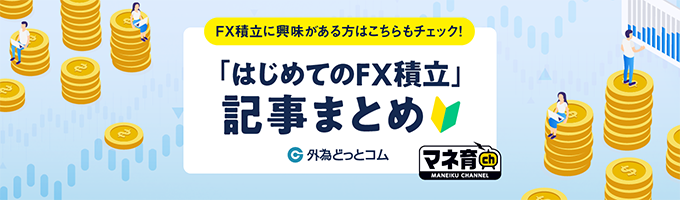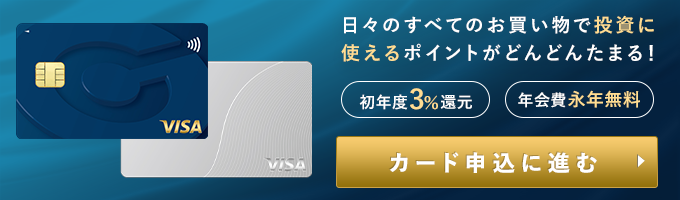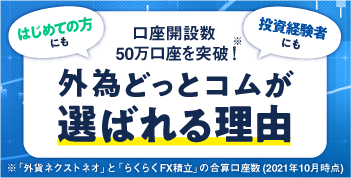外貨をより気軽に感じ、より簡単にお取引ができる外貨積立サービス「らくらくFX積立」をご紹介。
らくらく機能を多数搭載したスマホアプリよりご利用ください。
- 外貨積立(らくつむ)は『らくらくFX積立』の愛称になります。外国為替証拠金取引であり、外貨預金ではない点にご注意ください。
-
 外貨積立(らくつむ)の特長
外貨積立(らくつむ)の特長1通貨単位から始められるらくらくFX積立についてご紹介します。
-
 業界最高水準スワップポイント
業界最高水準スワップポイントFX積立『らくらくFX積立』口座において業界最高水準スワップポイントを付与いたします。
-
 スワップポイントカレンダー
スワップポイントカレンダー本日のスワップポイント、付与日数などを掲載しています。
-
 漫画でわかる!『外貨積立(らくつむ)』
漫画でわかる!『外貨積立(らくつむ)』少額から始められる投資をご検討の方必読の漫画です!
-
 お取引のルール
お取引のルールお取引についてのご注意事項など。ルールを十分にご理解の上、お取引ください。
-
 外貨積立(らくつむ)シミュレータ
外貨積立(らくつむ)シミュレータFX積立でスワップポイントがどのくらいになるのかシミュレーションできます。
-
 取引ツール
取引ツール取引ツールについて、インストール方法やご利用環境について。
-
 FXポイント
FXポイント獲得したFXポイントは、らくらくFX積立の買付注文にご利用できます。
-
 スワップ再投資
スワップ再投資貯まったスワップポイントを自動で振替え・再投資することができます。