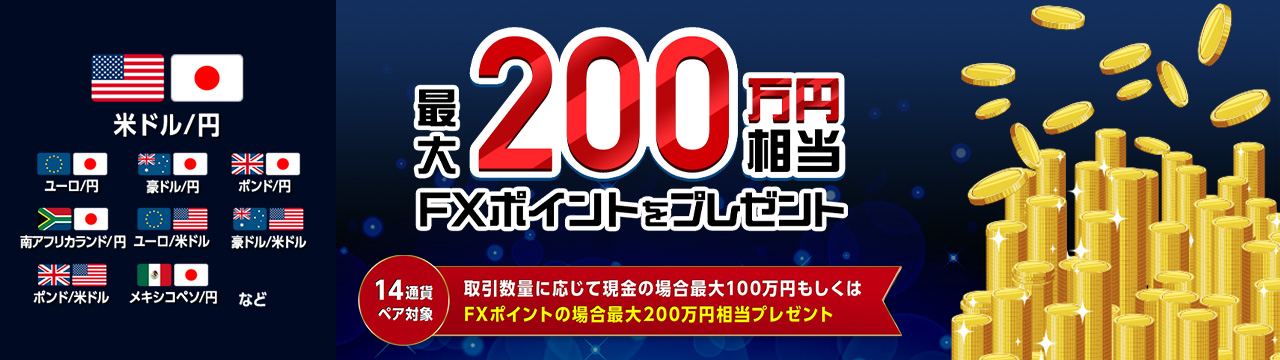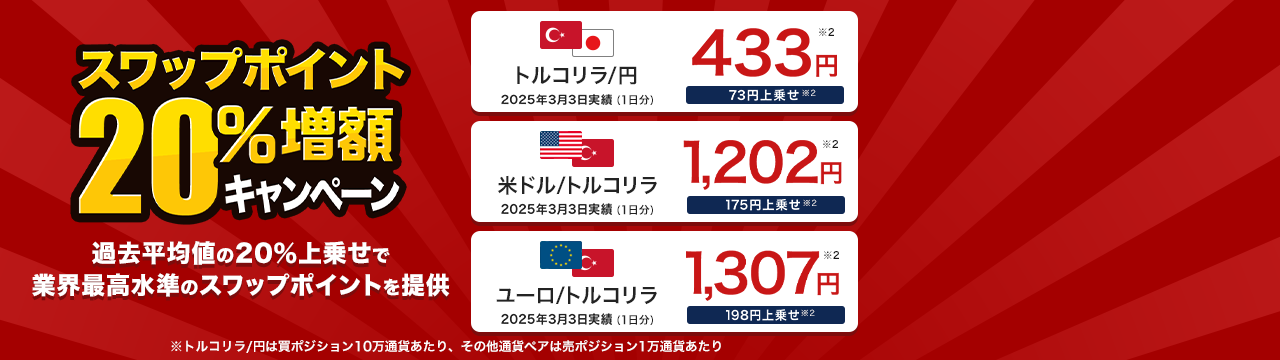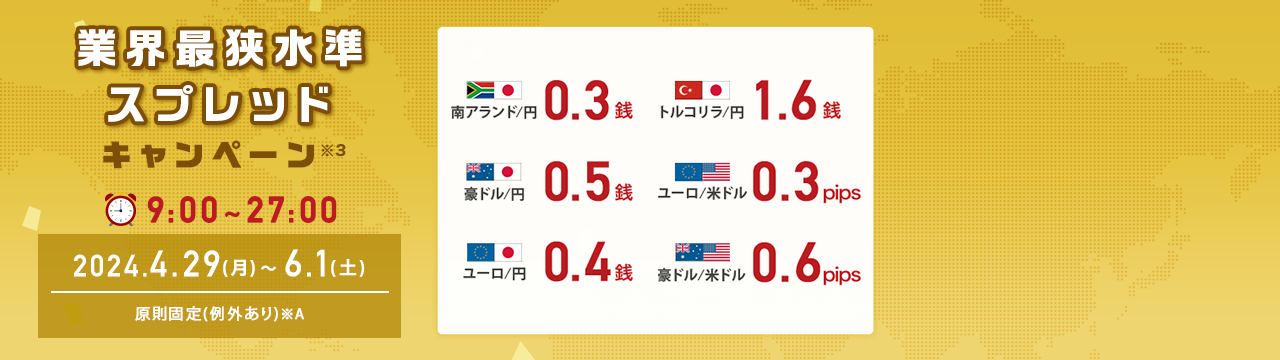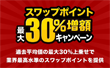はじめてのFXなら外為どっとコム
初心者から上級者まで
外為どっとコムが選ばれる理由
-

低コストの手数料・
取引単位 -

基礎から学べる
FX知識・セミナー -

安心・充実の
サポート体制 -

はじめてのFXに
最適なスマホアプリ -

業界最狭水準
スプレッド -

スワップ高水準の
高金利通貨 -

充実の会員様向け
キャンペーン -

取引機会を逃さない
マーケット情報
※買ポジション10万通貨あたり2024年3月適用分平均値
口座開設の流れ
「スマホで本人確認」を利用して申し込みを行えば、最短当日でお取引がスタートできます!※
-
フォーム入力 スマートフォンまたはPCから
本人情報をご入力ください。 -
本人確認書類の
提出お手元にマイナンバーと
本人確認書類をご用意いただければ、
PCからお手続きいただく方も、
スマートフォンを利用して
オンラインで本人確認が行えます。 -
口座開設完了 最短当日でお取引がスタートできます!
外為どっとコムのマーケット情報も
参考にして各種お取引を行えます。
新規口座開設でキャッシュバック
無料で口座開設
※ 法人のお客様を除きます。
また、日数はあくまで最短の目安であり、土日/一部の祝日を含む場合、提出いただいた書類に不備がある場合、
お客様の住まいの地域などにより異なります。詳しい手順はこちらをご確認ください。